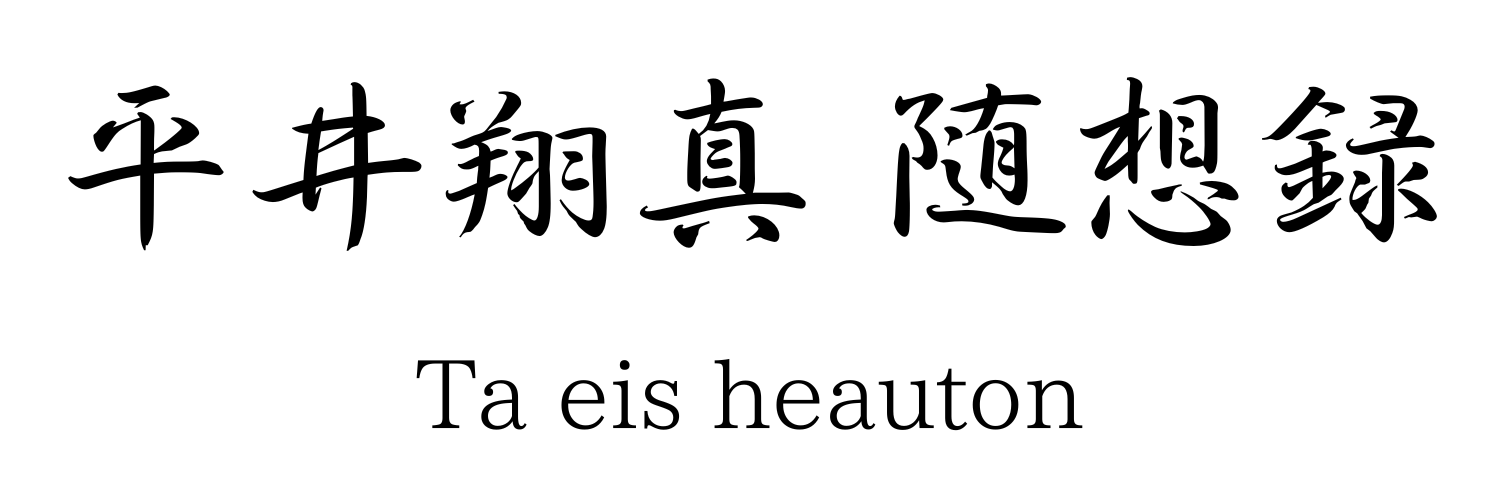援助について書きたい。
最初に断っておくが、ここに書くのは私が個人的な経験から立てた個人的な仮説と考えであること、データや何かをもとに構築した意見ではないあくまで感覚的な感想文であり、一種の偏見に近しいものであることを前提とさせていただきたい。
というのも、私自身はとくに援助を行なっている当事者ではなく、またその周辺領域におけるなんらのプロフェッショナルでもない。あくまで単なる一個人の所感であると思っていただきたい。
まずここでいう援助とは、いわゆる国際援助のこと。
日本などの先進国が、途上国に向けて行う国際協力の援助がそれだ。
アフリカの地で活動している限りで、この援助は切っても切れない関係になる。それはマクロでもミクロでも、アフリカをはじめとした途上国の至る所に存在する。
マクロで言えば、途上国で見かけるあらゆる建物や施設には、どこかの国の援助機関が支援をしたことを示す記念碑や印が付いていることが珍しくない。
学校や橋などははもちろん、井戸や道など、普通に生活していればかなり頻繁に援助によって作られたものが目に入ってくる。
そしてミクロで言えば、ストリートチルドレンなどが典型だろう。
道を歩けば子供達が寄ってきて、ご飯をくれ、お金をくれと要求してくる。
これもある意味で、これまで行われてきた援助によって、外国人はものをくれる人たちという考えが彼ら彼女らにインストールされていることの表れであり、援助の一面だ。
このように、マクロorミクロ関係なくあらゆるところに存在し、途上国とは切っても切れない援助について、以下の観点について言及したい。
援助はだれのためか?
援助は途上国のためであり、先進国のためである。
普通、援助と聞くと、奉仕や慈善の色が強く完全に途上国のためのものであると感じることが多いと思う。
そのイメージは間違っていない。
もう少し正確にいうと、援助はそのようなイメージをあえて被っている。
表面的には途上国のための慈善的な活動という見た目をしながら、実情としては先進国にとっても大きな利益をもたらすものが援助だ。
むしろ、そのように自らにとっても大きな利益があるから、先進国は援助を行なっている。
ここでいう先進国にとってのメリットとしては、大きく二つ、「該当の途上国との中長期的な関係性構築に役立つもの」「先進国の企業においてメリットとなるもの」が存在する。
前者について、これはいわゆる外交手段だ。
援助をしているという事実自体が意味を持ち、援助する側とされる側の関係性構築につながる。
途上国側からすれば援助をしてくれた先進国にたいする印象は少なからず良くなり、また先進国側からすれば将来的に該当の途上国が政治的、経済的に重要な影響力を持ち始めた時に備えて布石を打っておくことができる。
中長期的な視点で外交的メリットを得るための手段の一つが援助なのだ。
そして後者について。
こちらは少し具体例を挙げてみたい。
例えば、援助と題して途上国の港湾建設などを行うケースがよくある。
この背景には、港湾建設をすることが、先進国の企業が該当の途上国に対して貿易等での事業展開を行いやすくするなどの背景が存在する。
自国の企業活動を促進し、経済力を高めるため、また他国内での影響力を拡大するための土台づくりを国主導で行う。
援助はそのための一手段として活用される。
このように援助は受け取る側はもちろん大きなメリットを得ることができるが、実は与える側もメリットがあると見積もって実施をしている。
つまり、援助は受け取る側の途上国だけではなく、与える側の先進国を含めた双方にとっての活動になっている。
援助は彼らにとって死活問題か?
次に援助がなければ途上国になっては死活問題なのか?という点について考えたい。
ここについての答えとしては、「否」、つまり援助がなくても途上国がすべての援助対象者が急激に死活問題に直面することは少ないと考える。
その理由は援助を受けている現地に行けばよくわかる。
例えばアフリカのウガンダを例にする。
ウガンダでは国民の約40%が絶対的に貧困層に属しているとされている(絶対的貧困層:世界銀行の定義においては「一日に2.15ドル未満の生活を送る人」を意味する。)。
一方で、実際に現地を訪れてみると、この定義の問題に気がつく。
確かに世界銀行の定義の通り、ウガンダには「一日に2.15ドル未満の生活を送る人」がかなり存在する。
一方で彼らが、危機的な貧困状態にあるかと言われると、多くの場合においてそうではない。
なぜなら彼らは金銭的には確かに貧困層に位置するのだが、農作物や家畜などを豊富に持っており、物質的にはある程度豊かに暮らすことができているからだ。
かれらは1日に使える金銭の額はかなり少ないが、自らが育てた農作物や家畜をとおしてある程度の水準以上の暮らしを維持している。
つまり、先進国側のメガネを通して見た尺度ではたしかに貧困であるが、そのメガネを外して多様な軸で捉えると本質的には豊かなのだ。
彼らは援助はもらえるからありがたく受け取っているが、実は援助がとまっても急激に死活問題になることは少ない。
※ただし、HIVワクチンなど、現在援助によってのみ持続できており、援助がなくなると極めて大きな影響が起こりうるケースも存在している。
あくまで、援助がなくなるとすべてのケースにおいて死活問題になるか否か?という問いに対して、否であるということを改めて明記しておきたい。
援助は国を豊かにするか?
では、援助は本当に国を豊かにするのか?という点について考えてみたい。
ここについては、援助が間接的に国を豊かにすると考えている。
もう少し詳しく噛み砕くと、援助によって、企業の成長環境や、外資企業の参入環境が整えられることで、経済が成長し国が豊かになる。
つまり、援助をしているだけで勝手に国が豊かになっていくわけではないが、初期環境が整えられることで、経済成長の歯車が回り出し、結果的に国が豊かになるという流れだ。
例えば、前述したように、先進国は自国の企業が途上国に進出しやすくなるように港湾建設などの援助を行う。
この援助によって企業が途上国に参入すれば、流通する商品が増え、品質が上がり、また現地にたくさんの雇用を産む。
このように援助だけで国が豊かになることは少ないが、援助を通して環境が整い、間接的に経済成長につながっていくケースが考えられる。
アフリカはこの数十年間で経済成長をしなかった国だと言われる。
ただ、個人的な考えとしては、同じように援助を受けて環境が整った東南アジアや南アジア、南アメリカ諸国に先進国の各企業が進出したためにアフリカが手薄になり、結果アフリカのみが経済成長をせずに取り残される形になったのではないかと思う。
一方で、前述したアジアの国々などがかなり経済成長をしてきていることから、新しいマーケットを求めて多くの企業がアフリカに参入をしていくことになると思う(実際に現在かなりの外資企業がアフリカに進出を進め、参入企業数は急激に増加している。)。
つまり、これまでアフリカのみが取り残される形となってきたが、ここから数十年間はアフリカの年になっていくのではないかと思う。
そしてその末にアフリカ諸国は間違いなく経済成長を遂げ豊かになっていくはずだ。
援助について様々な視点で勝手な意見を述べてきたが、結論としては、「援助はする側もされる側もメリットがあり、中長期的な目線で見て国を豊かにしていくだろう」というのが、いま自分が感じている援助に対する所感だ。