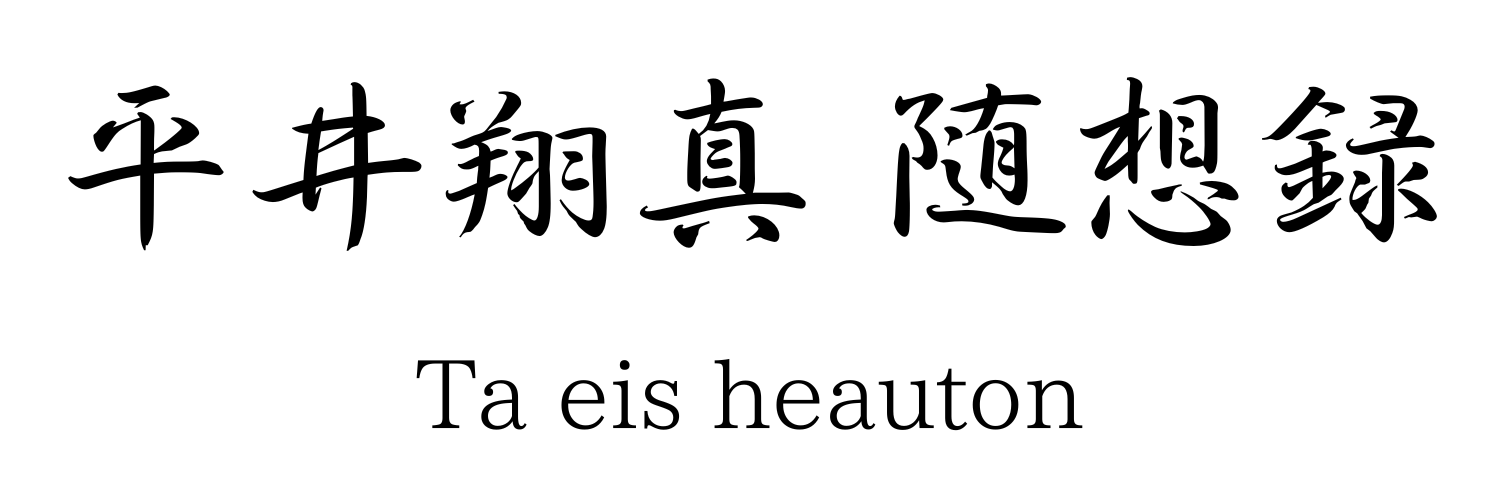前回の日記から1週間ほど開いてしまったので、週1週間分週1週間分の日記として記録しておこうと思う。この1週間のトピックは「休養、協力隊見学、NPO見学」。
休養
休養。そんなこともテーマになるのか?と思うかもしれないけど、なる。むしろ、この1週間での最も印象的なハイライトになってもおかしくないほど、重要だった。というのも先月の末、ほぼ1ヶ月前にアフリカに来てから、ほとんど休養を取らずに毎日何某かの活動をしていた。途中、1週間半ほどで、高熱を出して病院に罹ったが、とはいえ、即日で熱が下がったのでその後もあまり休養という休養をとっていなかった。が、ここに来て、疲れどっと溜まっているのを心身のいたるところから感じていたので3日ほど連続で休養日を作った。これを経て、やっぱり休養は大事、なんて当たり前のことを再確認した。体を休めるだけでなく、自分の思考を整理できるし、時間をとってゆっくり本を読むこともできる、それまでずっと風邪気味で声がほとんど出なくなっていたけど、この3日間の戦略的な休養で回復した。心も身体も、頭もしっかりリフレッシュできて、非常に良い休養となった。やっぱり人生は長距離走なので、定期的に休養をしっかりととり、無理をせずに長く着実にやっていくことが秘訣だなと痛感している。実はこれからアフリカの西の方に向けてゆっくり移動していこうと思っているのだけど、環境の変化や移動で心も身体もこれまで以上に負担を受けることになると思う。しっかり休養をとって、健康第一でやっていきたい。
協力隊見学
ケニアでJICA青年海外協力隊として活動している同級生の方にアポイントをいただき、活動現場に見学とお手伝いをさせていただいた。活動拠点は非行児童の更生施設。違法ドラッグや窃盗など軽犯罪を犯した児童(18歳くらいまでが対象)が、ここで数年間授業や職業訓練を受けて、社会復帰できるよう支援する国の施設。ここで彼は協力隊として活動している。主に農業を子供達に教えているとのこと。今回は施設内を見学させていただいた後、彼とも意見交換をし、最後に農場での農作業を一緒に実施させてもらった。思ったこと、感じたこととしては、協力隊のイメージが全く違うものだったということ。青年海外協力隊と聞いて、正直個人的にはJICAの活動の最も現場にいる人という認識だった。この「現場に最も近い」という認識自体は間違っていなかった。ただ、驚いたのは協力隊が行なっている実務はほとんどが各個人が計画から実行までを自分一人の裁量で行なっているということ。つまり、任地とテーマは与えられているが、あとはそこでどんなことをするのか、誰と協力するのかはほとんど自分で0から作るらしい。正直、決められた仕事を粛々としているという勝手なイメージを持っていたので非常に驚いた。彼をはじめ、協力隊の人には非常に能動的な人が多いなと思っていたが、実はそういう人でないとやっていけないほど、個人の能力が求められる現場だ。日系の大企業でエリートだとされている会社員のほとんどが、すぐに挫折してしまうほど難しい環境だと思う。個人的には、協力隊のイメージが非常に良い方にアップデートされた。途上国で何かやりたい、自分で将来的に何かやりたいけど、まずはその経験が手っ取り早くできそうなところはないかなと考えている人にはかなりお勧めできる。2年で任期が終わるというのも、強制的に次のステージに穂を勧めることになるので、非常に良いきっかけになると思う。
ちなみにだが、協力隊がこのような裁量の大きい仕組みになっている理由としては、「JICAをはじめ各国の国際協力機関は外交手段の一つである」ということ可能性の一つとしてある。外交上では「その現場で何をする」ということよりも、「その年度に何人の協力隊員を派遣してくれているのか」が重要になる。中身よりは形式や建前が重要ということの裏返しだ。「国際協力期間が外交手段の一つである」ということのわかりやすい例として、各国際協力機関は自国の民間企業の進出促進に繋がりそうな支援(港の整備で商社の進出を促進する)や、ライバル国との関係性を踏まえて牽制するために支援をするといったことがあげられる。正直、外交手段であるのはもちろんそうだろうと思うが、そうであっても、形式だけではなく、協力隊員の活動ももっと整備しなければ、あくまで国と国というレベルだけの活動となってしまい、現地の人や現場の協力隊員に対して本当に意味のある機会にはなりにくい。ここはアップデートしていくべき点であると痛感した。
NPO見学
(前提、今回参加させていただいたNPO単体に対しての意見や感想ではなく、NPOという構造自体に自分が持った思考であること、今回参加させていただいたNPOの方々は本当に精力的に活動をされていることを大前提として明記しておきたい。)
あるNPOの活動を見学&参加させていただいた。今回は、スラムの中で様々な支援を行う活動。その中の一つがゴミ拾いだった。スラムを流れる川の河川敷にゴミが大量の放棄されている。このゴミを全員でまとめて掃除していくという活動だ。しかし蓋を開けてみると、正直、課題がかなり見えてきた。これはあくまで僕の個人的な意見だが、感じたことを忘れないように書いておきたい。今回参加した活動は正直、本質的じゃない、と感じてしまった。スラムに住む女性たちと河川敷を掃除した。約30人の女性が参加した。活動は女性のエンパワーメントも目的にしている。実際彼女たちはしっかりとゴミを清掃していた。活動の写真も撮った。だけどよく考えてみると、本質的ではない気がした。彼女たちは、見返りとしてもらえる少しばかりの謝礼金を目当てにしていた。謝礼金が目当てだから、正直彼女たちにゴミ問題の意識はあまり高くない。現にゴミは片付けても片付けても、またそこに新しくゴミが溜まっていくらしい。活動した時間も十分と言えるほどではなかった。あくまで形式的にやっている感がやっぱり少し否めない。河川敷も、今回清掃したのはほんの一部で、見れば河川敷だけではなく川の中までゴミだらけだった。これでは彼女たちが少しのお金を得るために表面的な活動を形式的にやっただけとも捉えられてしまう。謝礼金にしても、たとえスラムであっても他の仕事で得られるようなもので、彼女たちにとってはその日は少し楽をしてお金を稼ぐことができただけになってしまう。これでは何も変わらない。世界は変わらない。そう思った。
原因は様々だが、クリティカルなのは、「当事者意識」「レバレッジ」の2点だと感じた。ゴミの清掃に対するインセンティブが当事者にとって薄い。だからこそ、当事者意識が低くなる。逆にこの清掃が自分たちの環境を劇的に変えたり、頑張れば頑張るほど報酬が高額になっていったり、周りの誰よりもゴミを清掃するインセンティブがあれば、当事者意識が一気に醸成される。また、レバレッジがかかっていないのも課題だ。たとえば、活動を通して得られる費用対効果が10倍だとすれば、今回投下された資本の何倍、いや下手をしたら10倍, 100倍の投資ができ、一気に活動の規模にレバレッジがかかるかもしれない。でもやはりリターンを目的にしていないNPOの形式だと、投資も大きくできず、レバレッジがかからない。この2点を踏まえて、やはりこの資本を中心とした資本主義界では、いかにビジネスの土台で物事を構築するのかが極めて重要だと再確認した。