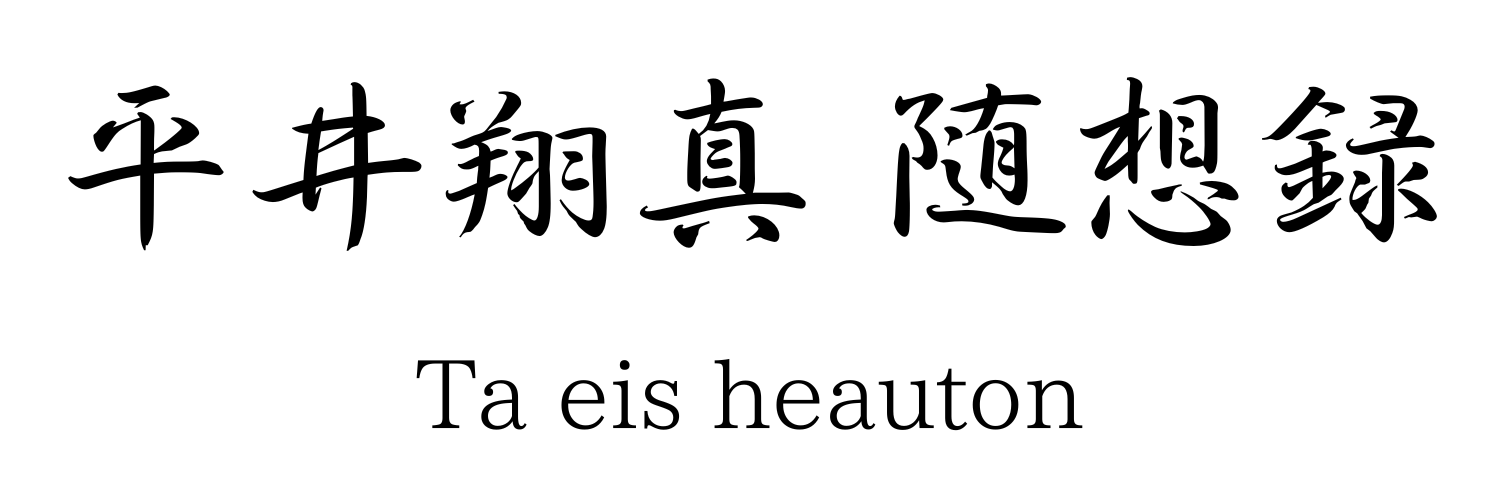ケニアの田舎に行ってきた。その地名は「ンマンダンドゥ村」。ケニアの首都ナイロビから北に2時間ほど車を走らせたところにある、ローカルな田舎町。標高は2,500mほどあるらしく、ケニアの中でも高山地帯に位置する。村の人は非常に伝統的な暮らしをしている。家で羊や牛、ロバなどを飼って暮らしている。もちろん自分たちで育てている家畜を毎日食事にしているわけではない。ただ、ナイロビのようにスーパーマーケットがあるわけでもなく、村には鶏肉屋、羊肉屋、八百屋、キオスク(生活用品を売っている)、などが点々としていて、各店で欲しいものを調達していくのが当たり前の世界。まるで、日本の戦前か、もっと言えば江戸時代くらいまでタイムスリップしたような感覚を感じる村だ。そんなところに、なぜ訪れるきっかけがあったのか。実はこの、ローカルの人以外をみることがないような土地で、イチゴ農家をやっている日本人の起業家がいる。その彼が、ちょうど自分と同級生で、彼の事業現場を見学&お手伝いさせていただくために、村を訪問させてもらった。3日間ほどの滞在で感じたこと、学んだこと、自分が考えたことをここに残しておきたい。
生きるということ
今回の経験を通して得たものは「生きる」ということに対する新しい角度。生きるとは何か、なぜ生きるのか、どのように生きるのか、生きるには何が必要なのか。生きるという概念に対するあらゆる考えに対して、新しい視点を与えてもらった。村の人たちは、シャワーは毎日浴びない。シャワーを浴びる日も、2日に1回ほど、桶に貯めた雨水を頭から被り汚れを落とす。寒くないように日中に浴びる。トイレはもちろん水洗ではない。小屋の中に穴が掘ってあり、そこで用を足す。水道もないので、雨水をタンクに溜めて使用する。雨水は沸騰させてチャイ(紅茶)にして飲む。ガスは通ってないので、焚き火で釜を温めその中でウガリ(現地の主食)を炊く。住むための家も基本自分たちで作る。何人かの大工を雇って自分たちも参加しながら少しずつ家を作る。レンガを使うこともあれば、地元のメイン産業の木材を使った家を作ることもある。羊やロバ、牛を飼い、畑でたくさんの作物を育てる。育った作物を食べ、足りないものは村の中の商店で調達する。祝い事の時には育てた羊をみんなで食べる。重いものを運ぶ時にはロバを使う。彼らはそうやって生きている。日本と比較してみると、大きなことも小さなことも、一つ一つ、全てが違っている。でもここの村の人も、日本に暮らす人も、僕もみんな同じく生きている。生きるとは何なのか、どう生きるのか、自分はどう生きたいのか、なぜ生きたいのか、何を感じて生きたいのかを考えた。答えなんて出ないけど、僕はなんとなく、この村での暮らしの方が「生きる」を身近に感じた気がする。生きるために作物を育て、生きるために水を貯め、生きるために動物を育て、生きるために食する。昼過ぎに突然の大雨が降ってきたら、作物が育つねと喜ぶ。雨で気温が下がり寒い中、みんなで家の中に集まって一緒にご飯を手掴みで食べる。日本での暮らしはとっても快適で便利で清潔で、日本で生まれ四半世紀を生きた自分にとって、それはとっても安心できる。だけど、生きているという実感を日本で暮らす日々の中でどれくらい感じてきただろうか、と考えるとあまり多いとは言えない。日本で暮らしているころは、北海道の広々とした大地を見たり、真っ赤に染まる夕焼けを見たり、大きな青空を見たり、どかっと積もった真っ白で綺麗な雪を見たり、そんな時にああ自分はこの地球に生きているなと感じて幸せになることが多かった。だけどこの村では、何が起きても何をしていても、「生きる」を感じる。多くのことが生きることに繋がり、その一つ一つから自分が生きていることを実感する。なんとなくだけど、僕はこの「生きる」が身近な生活に自分の心がワクワクしたし、すごく納得した気がする。
異彩の起業家
一人として日本人のいない、いやむしろ現地で生まれて現地で育った地元のケニア人以外いない村で、一人果敢に事業を行う日本人。26歳。逞しすぎる。カッコ良すぎる。自分と同級生にも関わらず、この環境で果敢に挑戦している姿を見て、正直、嫉妬を超えて心の底から尊敬した。本当に素晴らしい。尊敬したポイントは大きく3つ。「ユニークであること」「飾らないこと」「真っ直ぐであること」。AIとか、SaaSとか、人材会社とか、多くの人が知っていて、多くの人がすでに手を出している領域にチャレンジする人は実は意外とおおい。その是非を話しているのではなく、事実、すでに人が集まっているところに、さらに人はあつまる。稼ぎやすいとか、かっこいいとか、人がそう言えばいうほど、そこに人は集まり、コモディティ化する。しかし、ほとんどの人が一生の間に一度も想像すらしないようなことに挑戦する人はなかなか少ない。なぜなら、そういった領域を見つけるには、人の声をあてにせず、己の経験と思考と意志を掛け合わせて究極的にユニークさを突き詰めた先にしか見つけることができないから。彼はそれをやっている。ケニアの、ンマンダンドゥ村で、イチゴ農家を、現地の人とやっている。まさに異彩の起業家だ。そして彼は全く飾らない。自分をよく見せようと全くしないし、自分がやっていることを誰かに褒めてもらおうという様子すら全く見えない。自分が向き合っているコトと、一緒にやっているヒト、そしてジブンにだけ粛々と向き合っている。ありのままの等身大の自分であり続けている。そう彼は真っ直ぐなのだ。自分が今後取り組んでいきたいこと、会社や事業のビジョン、叶えたいこと、守りたいもの、それぞれに対して真っ直ぐに向き合っている。自分をよく見せようとしたり、周りからの見え方が気になったり、周りの意見を聞くことに安心を求めたりしない。真っ直ぐに戦う、まさに異彩の起業家だ。そんな彼に出会えたことを本当にありがたく、誇りに思う。
作業中に大雨が降ってやむなく作業を中断、家の中で暖まりながら彼と話した時間は、本当に楽しかった。僭越で勝手ながら、お互いすごく共感することが多かったし、持っている志もすごく似ている気がした。お互い、渋沢栄一が好きだということがわかり、なぜ好きなのかという話をして盛り上がった時、とっても素敵で楽しかった。
経験を経て自分は
今回は、本当に素敵で貴重な経験をさせてもらった。目まぐるしい日々ではなく、ショックなほどのカルチャーのギャップを感じたわけでもない。ローカルの暮らし、生き方、そこで戦う起業家を見て、心は落ち着きつつも、心の奥深いところで一つ一つにそうだよなと納得しながら、自分が大事にしたい、大事にしていきたいとと思ってきたものと繋がった気がする。今後の自分としては、やはり「生きる」ということに対する身近さや、自分がやることの本質性は大事にしていきたい。そして、彼のように、コト、ヒト、ジブンに対して真っ直ぐに、飾らず、自分軸で生きていきたい。今回の村で色々な経験をすることで、自分がやってみたいと思う新しいヒントを得ることもできた。(具体的には、人とのつながりや、人との共感、人と生きることができる場所づくりみたいなことはやってみたらすごく面白そうだと思った。)まだ完全に形にはなってないけど、一つ大事なかけらをもらった。今後色々活動していく中で、このかけらもどこかの一つのピースになって、自分の志を向ける先が形になっていったらいいなと思う。まだまだこれからもポレポレと前進していこう。